「ハイエースって引っ越しに使えるの。」と思ったことはありませんか。
自分で進める引っ越しは、段取りが分かれば想像以上にスムーズです。
この記事では、ハイエースでどのくらい入るのかをやさしく解説します。
荷室サイズの考え方や段ボールの目安、家電や家具の積み方まで順番にご紹介します。
初めてでも読み進めるだけで準備が整う構成にしています。
どこから始めればいいか迷う場面を想定して、手順を一枚にまとめました。
箱数の見積もりや、家電を運ぶ前のチェックポイントも入れました。
レンタカー選びと当日の流れも、やさしい順番で紹介します。
ハイエースの基本スペックと種類

ハイエースにはどんな種類がある?
ロングやスーパーロングなど、全長の違いがあります。
標準ボディとワイドボディで横幅も変わります。
標準ルーフ、ミドルルーフ、ハイルーフで高さの選択肢もあります。
引っ越しでは、荷物の高さと長さに合わせてタイプを選ぶのが近道です。
ドアの仕様もいくつかあり、片側スライドか両側スライドかで積み込みのしやすさが変わります。
床の高さが低めの仕様は台車の出し入れがしやすく、扱いやすいと感じる人が多いです。
駐車場や搬入口の高さに注意しつつ、
荷物の三辺を先に測ってから候補をしぼると迷いにくくなります。
同じハイエースでも年式やグレードで内寸が少し違うため、
予約前に寸法表を確認しておくと落ち着いて準備できます。
代表的な荷室の内側寸法の目安は、
- 長さ3,000mm(スーパーロングは3,540mm)
- 幅1,520〜1,730mm
- 高さ1,320〜1,635mm
です。
グレードごとのサイズ・寸法比較
標準ボディは取り回しがしやすく、段ボール主体の引っ越しに向きます。
ワイドやハイルーフは高さや幅にゆとりがあり、
棚やハンガーラックの直立配置がしやすくなります。
シートの使い方で荷室長が変わるので、当日は後席の状態も想定しておきましょう。
後席を起こしたままだと荷室長が短くなり、倒すと長物が入れやすくなります。
タイヤハウスの張り出しで床の有効幅が変わることがあるので、
箱の向きをそろえると並べやすくなります。
開口部の高さと幅もチェックして、家電や棚が通るかを玄関から車までの導線で確認します。
ハイルーフは室内高にゆとりがあり、ワイドは横幅にゆとりが生まれるため、
家具の姿勢を変えずに載せたいときに向いています。
積載重量と容積の目安
車両の仕様により上限は異なります。
箱だけで埋めるより、重さの合計も合わせて計画すると当日がスムーズです。
体積は「長さ×幅×高さ」でおおまかに把握できます。
段ボールの体積をそろえると見積もりやすくなります。
乗車人数の設定によって積める重量の上限が変わることがあるため、
何人乗るかを決めてから計算します。
容積の目安を出したら、充てん率を少し控えめに見積もると、
当日の並べ替えにゆとりが生まれます。
重い物は前方に、軽い物は上段に置く計画にして、バランスの良いレイアウトを考えます。
体積と重さのメモを作っておくと、積み始めてからの判断がスムーズになります。
車両総重量は「車両+乗員+荷物」の合計で考えます。
実際に積める!引っ越し荷物の具体例

家具類(ベッド、タンスなど)
シングルやセミダブルのマットレスは、斜めに入れるとレイアウトしやすいです。
棚は中身を抜き、引き出しはテープで留めると搬入が軽くなります。
脚が外せる家具は事前に分解してまとめるとスペースを活用できます。
マットレスはシーツや布団袋で包み、汚れやこすれを防ぐひと手間を入れます。
ベッドフレームは左右と中央の部材を束ね、ネジは小袋に入れて家具名を書きます。
タンスは引き出しを外して別々に運ぶと、持ち上げがぐっと楽になります。
テーブルの角は段ボールをL字に折って当て、上からテープで軽く留めます。
姿見やガラス棚は立てた状態で毛布に包み、壁側に寄せて固定します。
玄関や廊下の幅を先に測り、通りにくい物は向きを決めてから搬出します。
同じ種類の家具は並べて積むと、天面がそろって次の段が組みやすくなります。
家電製品(冷蔵庫、洗濯機など)
冷蔵庫は立てた状態で運ぶ前提で動線を考えます。
洗濯機は付属品やネジ類をジッパー袋にまとめ、前面に貼って紛失を防ぎます。
テレビは毛布や緩衝材で包み、倒れにくい配置を意識します。
冷蔵庫は中身を前日までに整理し、棚板やポケットを外してひとまとめにします。
扉はテープを短く貼って開かないようにし、持ち手側を外側に向けて運びます。
搬出経路の段差が大きい場合は、台車とベルトを併用してゆっくり進みます。
洗濯機はホース内の水を抜き、蛇口のキャップや部品を同封しておきます。
排水ホースの先端はビニール袋で包み、テープで口を閉じると車内が濡れにくくなります。
テレビは画面面を内側に向け、厚手の布で前後を挟んでから固定します。
リモコンやケーブルは透明袋に入れて、機器名を書いたラベルを貼ります。
設置後の手順が不安な家電は、取扱説明書を同じ箱に入れておくと迷いません。
冷蔵庫は縦向きで移動します。
ドラム式洗濯機は輸送用固定ボルトを装着してから移動します。
ダンボール箱は何箱載る?
箱のサイズをSとMにそろえると積み上げが安定します。
標準ボディではM箱をおおまかに数十個単位で計画するとイメージしやすいです。
箱の重さが偏らないように、重い物は小さめの箱へまとめると持ち運びが楽になります。
同じ向きで並べると天面がそろい、上に重ねやすくなります。
高さは三段から四段を上限にして、最上段は軽い箱にします。
本や食器は小さめの箱に分けると、移動の負担が減ります。
衣類やタオルは上段やすき間に入れて、揺れをおさえます。
箱の側面に部屋名と番号を書き、合計数をメモしておくと数合わせがしやすくなります。
長尺物がある日は、箱の列を一つ減らして側面に通路を作ると出し入れがスムーズです。
一人暮らし・二人暮らしの積載目安
一人暮らしはM箱中心で二十〜三十個と小型家具の組み合わせが目安です。
二人暮らしはM箱を増やし、
ベッドフレームやテーブルを分解して積むとスペースにゆとりが生まれます。
往復を前提にすると、無理のないレイアウトが組みやすくなります。
衣装ケースは中身を抜いて、軽い衣類だけを袋にまとめると載せ替えが楽になります。
ハンガーの服はハンガーボックスや衣類カバーを使うと、形を保ったまま移動しやすくなります。
自転車を載せる場合は前輪を外すと、空間にゆとりが生まれます。
往復プランは距離と時間で区切り、一便目は箱中心、二便目は家具中心にすると流れが整います。
手伝いが一人いるときは、積む人と室内で渡す人に分けると、作業のリズムがそろいます。
上手な積み込みテクニックと工夫

積み込む順番と配置のポイント
重い物は前方かつ低い位置に集めます。
軽い物は上段や手前に置き、取り出しやすくします。
開口部から見て左右の高さをそろえると、走行中の揺れに対応しやすくなります。
長尺物は左右どちらかの壁沿いにまとめて、中央は通路として十〜二十センチ残します。
扉がある家具は取っ手を外側に向け、開かないようにテープで軽く留めます。
箱の段差が気になるときは、空き段ボールを薄く折って下に差し込み、天面をそろえます。
重心が高くならないように、背の高い荷物は壁に寄せて、上部をベルトで軽く押さえます。
最後に取り出す物は奥へ、到着後すぐ使う物は手前に置いて、開口部の動線を広く保ちます。
固定ベルトや養生グッズの活用法
ラッチ付きのベルトで左右から挟むように固定します。
緩衝材や毛布で角を覆うと、こすれを抑えられます。
床に滑り止めシートを敷くと、箱や家具が動きにくくなります。
ベルトはねじれを作らず、金具が家具の角に触れないよう当て布を一枚挟みます。
床のフックは前後二点以上を使い、クロスするように張ると前後左右に効きます。
ネットやロープを天面に軽くかけて、上段の箱を押さえると安定します。
余ったベルトはまとめて結束し、走行中に垂れないようにします。
養生テープは塗装面を避け、取っ手や補強された部分に留めます。
パイプ用のクッション材や角当てを用意すると、接触が多い場所のこすれを抑えられます。
引っ越し荷物の仕分けのコツ
部屋ごとに箱を分け、箱の側面に行き先を書くと荷ほどきが早く進みます。
割れ物マークや「上に物を置かない」などのメモを大きく書きます。
当日に使う道具は別箱で手前に置き、すぐ取り出せるようにします。
箱に番号を振って総数をメモにし、積み込みと積み下ろしでチェックします。
「すぐ使う」箱には星マークなどの印を付け、玄関に近い場所へ配置します。
食器や本は小さめの箱に分けて、重さの偏りを減らします。
工具セット、延長コード、ゴミ袋、掃除用具はひとまとめにして、
最後まで見える場所に置きます。
貴重品や身分証は別の小さなバッグに入れて、常に手元で管理します。
旧居と新居で同じ色分けラベルを使うと、運ぶ人に伝わりやすくなります。
ハイエースで引っ越しする際の注意点

運転時の注意点と運転免許の条件
車体が大きくなると後方の見え方が変わります。
ミラーの角度を合わせ、発進前に死角を確認します。
普通免許で運転できる区分かを事前に確認し、無理のないルートを選びます。
普通免許の目安は「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2.0トン未満・乗車定員10人以下」です。
都市部の屋内駐車場は2.1m以下の制限が多めです。
ワイドやハイルーフには2.1mをわずかに上回る仕様もあるため、
現地の表示を確認してから進入します。
車幅感覚をつかむために、白線との距離を一定に保つ練習を出発前の低速で行います。
カーブでは内輪差が大きくなるので、早めに膨らまずゆっくり曲がります。
バック時はハザードで周囲に合図を出し、
必要なら同乗者に誘導をお願いすると落ち着いて動けます。
屋内駐車場や庇のある場所では全高を意識して、入口の表示を確認します。
雨や夜間は視界が変わるので、ミラーの水滴をふき取り、ライトの点灯をこまめに行います。
荷物で後方視界が狭まる場合は、左右ミラーとバックカメラを主に使い、
急な切り返しは避けます。
停車時は輪留めを使い、
坂道は前輪の向きを路肩側に少し切っておくと車両の動きを抑えやすくなります。
長時間運転は一時間から二時間ごとに休憩を入れ、車外から荷室のベルトの状態も見直します。
高速道路料金とガソリン代の目安
移動距離と区間で料金が変わります。
ETC割引の時間帯や、往復か片道かで合計額が違ってきます。
ガソリン代は給油回数を見込んで、合計の概算に含めておきます。
料金はルートを複数比較して、乗り降りするインターチェンジも含めて試算します。
深夜や休日の割引が使える時間帯は、到着時刻から逆算して出発時刻を決めます。
燃料の概算は「走行距離÷おおまかな燃費×単価」でメモにしておくと便利です。
満載時は加減速が増えるので、一定速度を心がけると消費の波を抑えやすくなります。
サービスエリアとパーキングエリアの給油所を事前にチェックして、
残量が三割になったら補給の目安にします。
レシートは返却手続きで使うことがあるので、封筒にまとめて保管します。
渋滞予測が出ている区間は、時間をずらすか一般道を挟む案も用意します。
荷物破損やトラブル防止の工夫
箱の積み上げは三段程度を基準にして、最上段は軽い物にします。
家電やガラス面は立てたまま、周囲を段ボールや毛布で囲みます。
走行中は休憩ごとにベルトの緩みを見ておくと落ち着いて進められます。
段差やカーブの手前では速度を落として、荷物の揺れを小さくします。
床面には滑り止めシートを敷き、空いたすき間にはクッション材や畳んだ布団を詰めます。
角当てを使ってテーブルや棚の角を覆い、こすれやキズを抑えます。
開口部から近い場所には軽い物を配置して、搬出時の持ち替えを減らします。
ベルトは左右からクロスするようにかけて、金具の位置が当たらないように布を一枚挟みます。
雨の予報がある日は、予備の養生テープとビニール袋を多めに用意して、
積み替え中の濡れを防ぎます。
夜間は懐中電灯やヘッドライトを使って、足元と荷室の固定ポイントを確認します。
レンタル利用時のチェックポイント
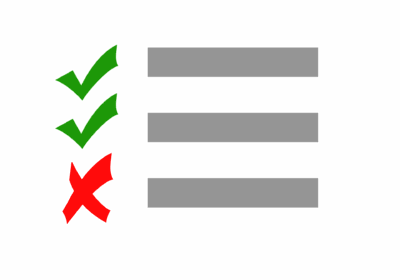
レンタル費用の相場と比較
時間制か日帰りかで料金が変わります。
週末や繁忙期の加算があるかを先に見比べます。
ボディサイズやグレードで単価が変わることがあるので、同一クラスで比較します。
ワイドやハイルーフは加算の設定がある場合があるので、条件表を確認します。
超過料金や延長の単価も事前に把握します。
走行距離の上限やキロ課金の有無を一覧でチェックします。
満タン返しの指定スタンドや給油条件も合わせて確認します。
Web会員の割引やクーポンの配布日をチェックすると計画が立てやすくなります。
店舗受け取りとデリバリー受け取りの違いも比較します。
返却は原則満タンです。
乗り捨て・返却オプションの確認
出発地と到着地が遠い場合は、乗り捨てが使えると移動が短くなります。
対応エリアと対象店舗、受付時間を先に確認します。
料金が固定か距離連動かで合計が変わるので、早めに見積を取り寄せます。
返却前の給油場所を地図アプリにピン留めします。
大型の駐車スペースがある店舗を選ぶと、返却時に落ち着いて動けます。
渋滞やエレベーター待ちを見込んで、返却時刻の前に余裕のバッファを入れます。
夜間返却ボックスの有無やキーの返し方も前日に確認します。
保険・補償内容のチェック
補償の内訳は対人、対物、車両、搭乗者などに分かれます。
設定されている免責額を確認し、免責補償の追加料金も把握します。
ノンオペレーションチャージの金額と発生条件を控えておきます。
ロードサービスの連絡先と受付時間をスマホに登録します。
連絡の順番と写真の撮影ポイントを三行メモにして、グローブボックスに入れておきます。
同乗者にも連絡先と予約番号を共有しておくと、その場での説明が短くなります。
引っ越しにハイエースを使う人の口コミ・評判

「思ったよりたくさん積めた!」
箱を同じサイズでそろえたら、並べやすくて作業が早く進みました。
当日は計画表どおりに積み込めて気持ちにゆとりが持てました。
事前に箱の中身を軽めに調整して、同じ高さにそろえました。
重い物を前に寄せて、軽い物を上に重ねたら、出し入れも迷いませんでした。
写真を撮って順番を記録したので、復路の積み直しも迷わず進められました。
「運転には少し慣れが必要だった」
最初は曲がり角が不安でしたが、ミラーとカメラをこまめに確認して落ち着いて走れました。
広い駐車スペースを探しておくと、乗り降りもスムーズでした。
最初は内輪差が読みにくくて、角で止まって確認する場面がありました。
目印になるポールを決めて、ゆっくり曲がるだけで気持ちに余裕が生まれました。
出発前に駐車場の出入り口を下見しておいたのも良かったです。
「節約できてよかった」
平日の割引と、友人の手伝いで人件の出費を抑えられました。
乗り捨てを活用して、移動の手間も短縮できました。
箱はリユースを活用して、梱包材は家にある毛布やタオルを使いました。
作業時間を午前と午後に分けて、休憩をはさみながら進めたら、無理なく終えられました。
返却時間に余裕を持たせたスケジュールにしたので、片付けの流れも整えやすくなりました。
まとめ:ハイエースは自力引っ越しの強い味方!

一人暮らしなら十分対応できる積載力
箱のサイズを統一し、重い物を前方に集めれば、無理なく積みやすくなります。
当日の作業ステップを事前に決めると、片付けまで一直線です。
持っていく物の優先順位を決めて、すぐに使う物は手前にまとめます。
家電のコードやネジは小袋に入れて、箱の外側に貼ると迷いません。
台車と軍手を用意して、搬出と搬入のリズムを整えましょう。
計画的な積み込みと準備でよりスムーズに
部屋別に箱を分け、動線をシンプルにすると搬入が早まります。
緩衝材と固定ベルトを合わせて使うと、車内のレイアウトが崩れにくくなります。
色分けテープで箱の行き先をそろえると、荷ほどきの順番が分かりやすくなります。
エレベーター待ちがある建物は、二人一組で受け渡しをすると移動が短くなります。
床や壁に当たりやすい角は、
段ボール板をL字にしてカバーすると作業の流れを整えやすくなります。
レンタル時は保険や返却条件も忘れずに
料金プランと返却方法を早めに確認し、当日のタイムラインに落とし込みます。
困ったときの連絡先を事前にメモしておくと、手続きで迷わず進められます。
営業時間と返却締め切りの時刻をカレンダーに入れて、到着予定から逆算します。
満タン返しのスタンドを地図アプリに登録しておくと移動がスムーズです。
距離制限や深夜の窓口対応の有無も前日に再確認しましょう。
連絡は電話だけでなく、
予約番号が分かるメールやアプリの画面も用意しておくと説明が短く済みます。


