運動会の名前って、毎年なんとなく同じになりがちですよね。
せっかくの一日だから、読み上げた瞬間に笑顔が広がる呼び方にしてみませんか。
このページは、やさしい言い回しで、すぐに使えるネーミングのコツと例をまとめました。
園や学校はもちろん、地域や社内でも応用できます。
ひらがな中心の案や、世界観をそろえる小さな工夫もご紹介します。
まずは一競技だけ、気軽に置き換えてみましょう。
読み上げやすくて、写真にも映える名前が、あなたの運動会をやわらかく彩ります。
読み手にやさしいことば選びなら、初めての方もすっと流れに乗れます。
投票や掲示のひと工夫も、最後まで楽しむきっかけになります。
準備も進めやすくなります。
なぜ“おもしろ種目名”が運動会を変えるのか?

名前ひとつで会場の雰囲気が盛り上がる
名前は最初の合図です。
読み上げた瞬間に情景が浮かぶと、始まる前からワクワクが広がります。
短くて言いやすいこと、リズムがあることがコツです。
口に出して気持ちよく言えるかを基準に選びましょう。
声に出して三回読んでも息が切れない長さにしましょう。
ひらがなとカタカナの割合をそろえると、読みやすさが続きます。
数字や色を少し入れると、競技の入口がすっと見えます。
子どもにも大人にも伝わる言い回しを心がけましょう。
司会の声の高さに合わせて、伸ばし音や促音の数を整えましょう。
看板とプログラムの表記をそろえると、名前の雰囲気がそのまま伝わります。
参加者と観客をつなぐ“ことばの演出”
同じ競技でも、呼び方で印象は大きく変わります。
「綱引き」より「綱キング決定戦」のほうが、観る人の気持ちが動きます。
名前に物語や役割を感じさせると、応援もしやすくなります。
読み上げアナウンスと名前のトーンをそろえると一体感が生まれます。
たとえば「台風の目」は「ぐるぐる旋風ダッシュ」と置き換えるだけで場面が立ち上がります。
チーム名やスローガンと語調を合わせると、覚えやすくなります。
放送原稿や掲示の文字サイズも名前に合わせて整えましょう。
観客の声がけの言葉も名前に沿わせると、会場の空気がまとまります。
合図の言葉を一つ決めて、入場から退場まで同じトーンで届けましょう。
ジャンル別!盛り上がるおもしろ種目名アイデア

定番をアレンジ!ひねりの効いた競技名
- 玉入れは「ラストスパート玉ラッシュ」。
- 大玉ころがしは「コロリンロード」。
- リレーは「ラストバトン大作戦」。
定番の動きを一語足して、目的や雰囲気をわかりやすく伝えましょう。
- 障害物走は「ドキドキ障害ロード」。
- 大縄とびは「ジャンプジャンプ大道」。
- 台風の目は「ぐるぐる旋風ダッシュ」。
- 綱引きは「綱キング決定戦」。
色や数字を入れると、ルールのイメージがすっと伝わります。
言葉は短く、声に出して読みやすい音をえらびましょう。
看板やプログラムと同じ表記でそろえると、会場全体のトーンがまとまります。
物語風・必殺技風:世界観で魅せるネーミング
- 「勇者たちの大玉ロード」。
- 「忍者のしのび足リレー」。
- 「伝説の綱合戦」。
世界観を先に決めると、名前も演出も統一しやすくなります。
- 「姫をまもれ騎士リレー」。
- 「影の術ダッシュ」。
- 「星空クエスト玉入れ」。
- 「城下の石畳スプリント」。
テーマは一つにしぼり、色と小道具でそろえましょう。
読み上げの合図とリズムを合わせると、耳に残りやすくなります。
漢字とひらがなのバランスを整え、長くなりすぎない名前にすると読みやすいです。
親子・キッズ向け:かわいくて伝わりやすいネーミング
言葉はやさしく、語感は軽やかに。
- 「おやこでジャンプぴょん」。
- 「みんなでコロコロ」。
ひらがな中心で、行動がイメージしやすい名前にしましょう。
- 「てをつないでゴールだよ」。
- 「ぴょんぴょんバトン」。
- 「にこにこボールリレー」。
小さな声でも読み上げやすい音を選びましょう。
数字や色を入れると、ルールが伝わりやすくなります。
プログラムやゼッケンもひらがなを合わせると、流れがすっきりします。
社内・地域イベント向け:印象に残るユニークな名称
自分たちだけがわかる固有名詞を少し混ぜると、ぐっと“自分ごと”になります。
- 「部署横断バトン」。
- 「○○プロジェクト駅伝」。
会場の雰囲気に合わせて、フォーマル寄りかカジュアル寄りかを選びましょう。
地名や商店街の通称を入れると、地域に寄りそった空気になります。
社名の略称やプロダクトの愛称を一語添えるだけでも、ぐっと親近感が出ます。
- 「○○タウンリレー」。
- 「スプリント of ○○部」。
表記ゆれを避けるために、プログラムで統一の書き方を決めておきましょう。
看板やハッシュタグも同じ書き方にそろえると、目に留まりやすくなります。
観客参加型:応援や拍手が勝敗を左右する種目名
- 「拍手ポイント対決」。
- 「応援ジャンケンリレー」。
観る人の行動が名前から伝わると、参加のハードルが下がります。
ゴール演出と名前をペアで考えると記憶に残ります。
- 「て拍子ラリー」。
- 「声コールチャレンジ」。
- 「ウェーブでつなぐバトン」。
司会の掛け声とテンポが合うと、自然に一体感が生まれます。
採点の仕組みはボードに大きく掲示して、いつでも見られるようにしましょう。
写真といっしょに合図のポーズを描いておくと、初めての方にも伝わりやすいです。
そのまま使える!おもしろ種目名テンプレート集

プレフィックス×競技名×サフィックスで簡単に
- 頭語に「参勤交代」「必殺」「伝説の」を置きます。
- 真ん中に「綱引き」「大玉」「リレー」を入れます。
- 語尾に「大作戦」「グランプリ」「合戦」を重ねます。
三つを組み合わせるだけで、短時間で多くの案が作れます。
頭語は三音前後にすると、呼びやすくなります。
真ん中の競技名は校内放送で聞き取りやすい語を選びます。
語尾は「チャレンジ」「ロード」「グランプリ」など雰囲気に合わせて使い分けます。
ひらがなとカタカナのバランスを整えると、読み手の迷いが少なくなります。
カードに書いて声に出し、テンポをたしかめると仕上がりがまとまります。
三案ずつ束ねてチームに配ると、投票までの流れがスムーズになります。
例:参勤交代リレー/サンダーストライク綱引き/おやこジャンプ合戦
- 「参勤交代リレー」。
- 「サンダーストライク綱引き」。
- 「おやこジャンプ合戦」。
語感を声に出して確認すると、読み上げやすさが見えてきます。
- 「ギガコロリンリレー」。
- 「忍者ダッシュ合戦」。
- 「コズミック玉ラッシュ」。
語尾だけを入れ替える練習をすると、量産が進みます。
読み上げる人の声の高さに合わせて、伸ばし音や促音の数を調整します。
初めての方は、三語構成を基本にすると迷いません。
おもしろ種目名アイデア集【実例付き】

和風ネーミング例
- 参勤交代ロード(リレー)。
- 五右衛門縄とび(大縄跳び)。
- 陣取り綱合戦(綱引き)。
- 大俵ころがし(俵転がし)。
- 忍び道リレー(リレー)。
- お城めぐり駅伝(リレー)。
- 大名行列バトン(リレー)。
- 竹取ラン(徒競走)。
隊列入場を「出陣」と呼ぶと、全体のまとまりが出ます。
扇子や和柄のアイコンを合わせると、名前の雰囲気がすっと伝わります。
英語・カタカナ系ネーミング例
- サンダーストライク綱(綱引き)。
- ギガ玉入れ(玉入れ)。
- メガリレー(リレー)。
- クロスロープバトル(十字綱引き)。
- ライトニングリレー(リレー)。
- ロイヤルロープ(綱引き)。
- スターランウェイ(徒競走)。
- コズミックダッシュ(徒競走)。
英語は短く、読みやすい音を選びましょう。
三〜四音でそろえると、呼びかけがすっきり聞こえます。
親子参加向け・園児向けネーミング例
- いっしょにゴール(親子競走)。
- おやこでボールぴょん(親子ボール運び)。
- なかよしミニリレー(リレー)。
ことばはひらがな中心にして、行動が想像できるようにします。
- おやこでバトンぽん(親子リレー)。
- てをつないでゴール(親子競走)。
- みんなでよーいどん(徒競走)。
- にこにこ玉ひろい(玉入れ)。
声に出して読んだときの音のやわらかさを大切にしましょう。
ひらがなとカタカナの比率を整えると、読みやすさが続きます。
観客を巻き込む仕掛け系ネーミング例
- 拍手で逆転ショー(応援企画)。
- 応援ジャンケンステージ(じゃんけん企画)。
- コール&レスポンスリレー(リレー)。
名前に観客の動作を入れて、参加のきっかけを作りましょう。
- 拍手カウントリレー(リレー)。
- ウェーブ応援タイム(応援企画)。
- 歓声ポイント合戦(応援企画)。
- 笑顔スタンプラリー(スタンプラリー)。
司会の合図と名前のリズムを合わせると、場のまとまりが生まれます。
ゴールの合図といっしょに拍手をお願いすると、自然に参加の輪が広がります。
おもしろ種目名を活かす演出アイデア

BGM・衣装・道具で世界観を演出
名前に合わせて、色と形をそろえます。
旗やゼッケンの色、コーンの並べ方を統一します。
衣装や小道具は写真に写る面を意識して選びます。
入場口の立て看板も同じトーンで作ると、会場全体がまとまります。
カラーパレットは三色までに絞ると、視線が迷いにくくなります。
競技名カードと同じ色でコーンや旗を選ぶと、統一感がぐっと伝わります。
衣装は動いたときの揺れがきれいに見える素材を意識すると、写真にリズムが生まれます。
MCの呼びかけと名前のリズムを合わせると、入退場の流れがなめらかになります。
屋内は照明の色、屋外は日陰の位置を見て、撮影しやすい列を作りましょう。
応援ボード・フォトスポットで記憶に残る空間づくり
チームごとに応援ボードを用意します。
名前のロゴを貼ると、写真にメッセージが映ります。
フォトフレームや背景布を入口に置くと、投稿のきっかけが生まれます。
サイズはA3以上にすると、遠くからも読み取りやすくなります。
縁にチームカラーのテープを貼ると、区別がしやすくなります。
並べる場所は入口と観客席の通路沿いにすると、目に入りやすくなります。
屋外ならラミネートやクリップを用意して、掲示が崩れにくい形に整えましょう。
SNS投稿につながるハッシュタグ活用法
ハッシュタグは短く、読みやすく。
チーム名とセットで掲示すると迷いません。
プログラム最終ページに一覧を載せて、いつでも見返せるようにします。
数は二つまでにして、英数字は小文字でそろえましょう。
掲示やプログラムにQRを添えると、投稿までの流れがスムーズになります。
投稿例の一行を用意して、絵文字や区切り記号の使い方を示すと、まねしやすくなります。
種目名の決め方:みんなで楽しむ工夫
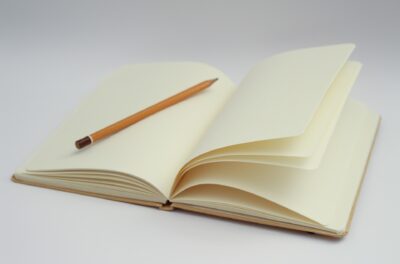
候補を出して投票!事前参加型ネーミング
候補を三つまでに絞り、発表します。
事前投票で選ぶと、当日の期待が高まります。
投票用紙やフォームは、学年や部署ごとに色分けすると集計が楽です。
紙とオンラインの二本立てにすると、参加のきっかけが増えます。
締め切りは前日夕方など、迷わない時間をはっきり伝えましょう。
同票のときは再投票や司会のじゃんけんなど、決め方を先に知らせます。
投票箱やフォームのタイトルは世界観に合わせて、楽しい見た目にします。
結果発表の前に、上位案の読み上げ練習をしておくと進行がなめらかになります。
子ども・社員に名付けを任せて盛り上げる
名付けを任せると、主体性が生まれます。
選ばれた名前の由来を放送で紹介すると、会場がやさしい空気になります。
表彰や記念シールを準備して、関わりを形に残しましょう。
ルールは文字数や使ってよい表記を共有して、迷いを減らします。
由来は一言コメントにして、プログラムや掲示に載せます。
名付けメンバーの紹介カードを入口に置くと、雰囲気がやわらかくなります。
記念シールはチームカラー違いで用意すると、持ち帰ってうれしい思い出になります。
参加できなかった人向けに、次回用のアイデア箱を置いて、いつでも提案できる場を作ります。
借り物・借り人競走をもっと楽しむための工夫

お題の選び方:色・形・条件でわかりやすく
お題は色や形で指定します。
- 「赤い帽子」
- 「丸いキーホルダー」
- 「青い表紙の本」
のように、誰でも探しやすい基準にします。
持ち歩きやすい物を中心にすると進行がスムーズです。
サイズや素材もざっくり示すと迷いが減ります。
例として「小さめのタオル」「軽いボール」のように書き添えます。
会場にサンプル写真を掲示すると、探す流れが早くなります。
お題カードの色を分けて、学年やチームごとに区別します。
返却かごの位置をスタート前に案内すると、戻す動きが整います。
時間にゆとりがないときは、お題を「色だけ」「形だけ」にしてシンプルにします。
トラブルを避けるためのポイント
人を探す場合は、条件を中立にします。
「同じ色のリストバンドの人」「同じチームの人」のように、
見た目の評価に触れない言い回しにします。
借りた物はゴール後にすぐ返す流れをアナウンスに入れましょう。
声かけの文面は事前に決めて、同じ言い回しで案内します。
返却場所はゴール横のかごに統一し、矢印で示します。
持ち主がわかるように、付せんやタグを用意して貼れるようにします。
見つからない場合の代替案を決めておき、「次のお題へ進んでOK」と司会が伝えます。
人を探すお題は「同じ色のゼッケンの人」「同じ番号のレーンの人」なども使いやすいです。
年齢・立場別に変えるネーミングのコツ

園児〜小学生向け:ひらがな+語感重視
言葉は短く、やわらかい音で。
動作が浮かぶことを最優先にします。
ひらがなを多めにして、読みやすさを大切にします。
繰り返しのことばやオノマトペを入れると、口に出したときにリズムが整います。
色や形の言い回しを足して、見ただけで動きがわかるようにしましょう。
名札やプログラムはひらがな表記で統一すると、読みやすさが続きます。
中高生・地域:語彙+ユーモアで印象づける
言葉に遊びを入れて、物語を感じさせます。
英語やカタカナはアクセントとして使います。
チーム名やスローガンと合わせて、全体のトーンをそろえます。
カタカナ語は三音か四音までにすると、呼びかけが心地よく響きます。
比喩は一つだけにして、長くしすぎないことがポイントです。
社内:部署・商品・会社ネタの活用法
社名やプロジェクト名を少し混ぜます。
「○○横断リレー」「○○チャレンジ駅伝」のように、内輪のキーワードで親近感が高まります。
表記は社内ガイドラインに合わせて整えます。
部署名の略称やプロダクトの通称を短く添えると、呼ばれた側の気持ちがぐっと近づきます。
周年テーマや社内スローガンと組み合わせると、当日の掲示物とも相性がよくなります。
まとめ:運動会をもっと自由に、おもしろく
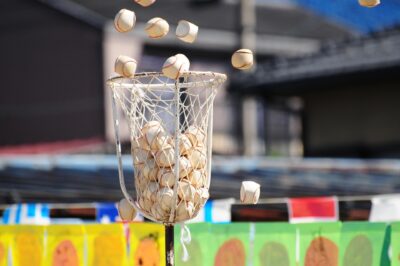
おもしろ種目名で記憶に残る1日に
名前が変わると、気持ちの温度が上がります。
世界観をそろえると、写真と記憶に残ります。
まずは一競技から、やさしく試してみましょう。
次はプログラムの見出しも同じトーンにそろえましょう。
読み上げの練習をして、声に出したときの響きをたしかめましょう。
看板やビブスに同じ言い回しを入れると、ぱっと見で伝わります。
色とアイコンを合わせると、名前の雰囲気がすっと届きます。
小さな一歩でも、次の開催につながる種が育ちます。
読者が今すぐ使えるヒントの振り返り
定番に一語を足す。
世界観を先に決める。
声に出して読みやすいかを確かめる。
事前投票で名前を決める。
応援の動作を名前に入れる。
この五つで、今日から企画が動き出します。
時間があれば、アナウンス原稿と掲示の文面も同じ表記でそろえましょう。
見出しとロゴをカードにして配ると、準備が楽になります。
ひらがなとカタカナの割合を調整して、読みやすさを大切にしましょう。


